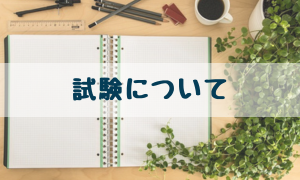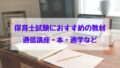独学で保育士試験を目指すときに一番の壁になるのが、どうやって勉強時間を作るか?ではないでしょうか。
子育て中だったり、フルタイムで働いていたりすると、「机に向かって何時間も勉強」なんて正直むずかしいですよね…。
実は私自身も、もともとコツコツ勉強するタイプではありませんでした。
そんな私でもスキマ時間の使い方を変えただけで、少しずつ勉強が習慣になり、合格までたどり着くことができました。
この記事では、
- 朝・昼・夜・寝る前のスキマ時間の使い方
- 休日の勉強の進め方
- 忙しい人でも続けやすい工夫
を、実体験からまとめてみました。

「時間がないから無理かも…」
そう感じている方のヒントになればうれしいです。
保育士試験の勉強が続きにくい理由

保育士試験の勉強が大変だと感じる理由は、「内容が難しいから」だけではありません。
試験の内容を調べたときに多くの人が不安になるのはこの3点です。
- 出題範囲が広く、何から手をつけていいか分からない
- 暗記と理解、両方が必要
- まとまった勉強時間が取りにくい
保育士試験は、長時間の勉強よりも「積み重ね」 がとても重要になります。
勉強時間は「まとめて」ではなく「分けて考える」
「今日は2時間勉強しよう!」と思うと、それだけでハードルが上がってしまいます。
家事などに追われてドラマを1時間見ることだって難しいのに、勉強なんてなおさらですよね😔
勉強でおすすめなのは、1日の中のスキマ時間を細かく分けて使うこと。
そして平日と休日で勉強のやり方を変えることです。
次から説明していきますね。
平日の勉強時間のイメージ
- 朝:5~10分(朝は忙しいので、毎日じゃなくてOK!)
- 昼:10〜15分
- 夜:10~20分前後
合計すると、1日30分〜1時間弱の時間になります。
少しずつですが、確実に力がついていきます。
朝・昼・夜・寝る前のおすすめ勉強法

朝(出勤・子どもの送り出し前)
- 頭が一番スッキリしている時間
- テキストを読むなどの簡単なインプット
- 暗記系の確認に向いている
朝はとにかく忙しいので、できるだけでOK。
前日に暗記した内容を軽く見返すだけでも効果がありますよ~。
昼(通勤中や休憩時間)
- 一問一答問題を解く
- 単語集や用語チェックなどの軽めのアウトプット
状況にもよりますが、時間に合わせて区切れる勉強をするのがおすすめ。
なにか邪魔が入ってもすぐ切り上げられるようにしておくと、覚えている最中の用語が飛ばなくてすみます😊
夜(帰宅後)
- 家事をしながら動画や音声を流す
- テキストを開けない日でも「耳だけ勉強」
私は夕食の支度中に、YouTubeの解説動画を流していました。
通信講座の動画教材を使用するのもいいですね!
寝る前
- スマホで問題を1問ずつ解く
- 眠くなったら無理せず終了
正直、そのまま寝落ちする日も多かったですが、それでもヨシ!
休日の勉強は「過去問」に集中する
平日はとにかく忙しいので、勉強時間を確保するのではなく、余った時間を勉強時間にするようにしていました。
その分、休日は机に向かって過去問をみっちり行いました!
それでも、
- 30分〜1時間でも十分
- まとめて何年分もやらなくてOK
- できないときは平日の勉強法に切り替える
- 休むための休日も確保する
と、とにかく無理はしないようにしました。

時間とやる気があるときは1時間超えて勉強しました!
(めったにない)
おすすめの流れは、
- 過去問を解く
- 間違えた問題にふせんをつける
- 解説を読んで理解する
- ふせんの付いている問題を解く→解けるようになったらふせんを外す
これをくり返すと、少しずつ「解ける問題」が増えていきます。
完璧を目指さない

今、こんな感じで書いていますが、一時期はほんっとーーーに勉強が嫌で、始めたことすら後悔した時期もありました。
勉強が続かなかった頃の私は、
- 今日もできなかった…
- またサボってしまった…
と、よく自己嫌悪になっていました。
でも今思うと、できない日があって当たり前 。
- 勉強できた日はエライ!
- 勉強ができなかった日は、仕事や家事を頑張ったからできなかった!
くらいの感覚で十分。
続けることのほうが、一日一日の量よりずっと大切です。
👇しんどかった時のお話しはこちらから。
実技試験について
筆記試験に合格すると、実技試験があります。
- 造形
- 音楽
- 言語
この3分野の中から2分野を選択します。
実技は試験の申し込み段階で選択するため、早めに「自分に合いそうな分野」を決めておく のがおすすめ。
👇実技についてはこちらからどうぞ。
まとめ|スキマ時間の積み重ねが合格につながる
保育士試験の勉強は、長時間やることや毎日完璧にこなすことよりも「少しずつでも続けること」 が一番の近道です。
朝・昼・夜・寝る前。
ほんの数分でも、積み重ねれば大きな力になります。
無理のないペースで、あなたの生活に合った勉強スタイルを見つけてくださいね。